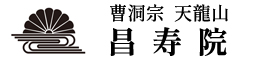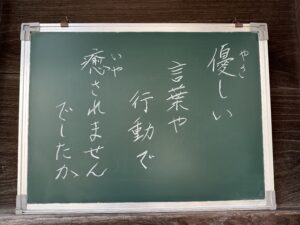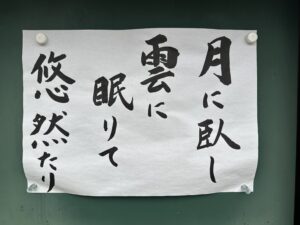第7教区護持会 地区布教役員研修会 出講(報告)

令和7年6月16日(月)~20日(金)に「京都府宗務所 第7教区護持会 地区布教役員研修会」で法話をさせていただきました。
第7教区では毎年ブロックごとに護持会役員の方々が参加して、研修が行われているとのことで、今年度は私が宗務所布教師として、60分間のお話をさせていただくきました。
5日間・5会場で開催され、護持会役員の皆様をはじめ、各会長のお檀家さん、そして教区長 大倉由照 老師のご尽力のもと綿密な準備と運営がなされており、敬服した次第です。
これまで他の檀家さんに向けて、まとまった話をすることはほとんどなかったのですが、様々なお寺にお邪魔して、多くのお檀家さんとご縁をいただく大変貴重な経験となりました。厚く御礼申し上げます
今回、「利他」をテーマにし、『まんまるな生き方を目指して~利他の心』と題してお話しました。放送中のNHK連続テレビ小説「あんぱん」を導入として、あらためて、仏教の目指す理想の利他行について考えました。日本人は、子どものころから「人の為に」行動することが教えられ、自然に身についていると感じています。しかし、その利他的な行いが、知らず知らずのうちに、自分の苦しみの原因となっていることもあります。そのあたりにもふれながら、お話ししました。
会場(令和7年6月16日~20日)
- 常昌寺(園部町内林西畑)
- 法積寺(園部町半田北)
- 延命寺(八木町玉ノ井里ノ内)
- 西福寺(園部町横田)
- 永昌寺(園部町熊原山ノ口)
演題「まんまるな生き方を目指して~利他の心~」
昌寿院 大井龍樹
(当日の法話より抜粋)
本日は、「まんまるな生き方を目指して ~利他の心~」と題してお話させていただきます。
「利他(りた)」とは他を利すると書きます。その反対は「利己」です。
お寺の世界ではよく使う言葉ですが、皆さんはどうでしょうか。
利他とは、他人に利益を与えること。他人の幸福を願い行動すること。
そして、そのような利他的な行いを「利他行(りたぎょう)」といいます。
仏教では、「利他」と対になる言葉として「自利(じり)」という言葉があります。
自らを利すると書く。“自分の利益”という意味と、“自分の修行、自分の悟り”という意味も含んでいます。
大乗仏教では利他行を重要視しています。
コロナ禍において「利他」が注目されました。
パンデミックにおいて、利他的な行為とは何か、という議論が沸き起こりました。
日本人にとっては「マスクをする」ことや外出しないことは、利他的な行為という認識はあまりないと思うのですが、自分のしたいこと我慢する、国によっては利他的な行いと捉えたようです。
また、人とのつながり疎遠になったことで、かえって、人とつながること、「利他」が注目されました。
今日は利他についてそして、仏教の目指す利他とは何かで考えてみたいと思います。
「アンパンマン」に込められた思い
今NHKで放送されている連続テレビ小説『あんぱん』、ご覧になっておられますか?
視聴されている方、手を挙げていただけますか?――おっ、けっこういらっしゃいますね。
このドラマは、絵本作家・やなせたかしさん夫妻の人生を描いた物語で、主人公は妻のノブさん。史実をベースにしながら、創作も交えて構成されています。
ご存じのとおり、やなせたかしさんは、あの国民的キャラクター「アンパンマン」の生みの親です。
「アンパンマン」名前は皆さんご存じだと思います。実際にどんなキャラクターで、どんな物語か、ご存じでしょうか?
私などは、アンパンマンに足を向けて寝られないほどです。我が子も小さいころ本当にお世話になりました。特に1歳から3歳ごろの子どもにとっては、アンパンマンは絶大な人気です。
ご存じない方もいらっしゃるかもしれませんので、簡単に説明します。
アンパンマンは、パン工場でジャムおじさんによって作られた「アンパンの顔をしたヒーロー」です。
最大の特徴は、自分の顔――つまり“あんパン”でできた顔を、困っている人や空腹で倒れそうな人に差し出し、食べさせるという点にあります。
なんとも不思議なヒーローですが、 これがアンパンマンの物語の核となっています。
アンパンマンはもともと絵本として発表されました。 (やなせさん年齢:絵本出版1973年(54歳)・TVアニメ化 1988年(69歳)・94才で死去)
ですが、初期の評価は決して良いものではなかったそうです。
初めて見ると、顔をかじらせる。顔のないヒーローが空を飛んでいる……というシュールな光景に、眉をひそめる大人もいたそうです。
しかし、子どもたちにはとても人気がありました。真正面からアンパンマンを受け入れた。
そしてやがてアニメ化され、大きな人気を博し、今や、三番目の長寿アニメ番組。今やだれもが知る日本を代表するキャラクターとなったのです。
-------------------------------------------------------
アンパンマンが生まれた背景には、やなせたかしさんの戦争体験がありました。
やなせさんは、1941年に22歳で招集され、1943年(24歳)から終戦まで中国大陸で従軍されました。
ドラマにも登場する、最愛の弟・千尋さんもこの戦争で命を落としています。
中国大陸で、やなせさんは厳しいの飢えを経験します。
「人生で一番つらいのは、食べられないことだ」と深く実感したといいます。
やなせさんの著書『アンパンマンの遺書』には、こんな記述があります。
「正義はある日突然逆転する。正義は信じがたい」
では、正義はこの世にないのか?
「逆転しない正義とは献身と愛だ」
では、その献身と愛とは何か?
「それも決して大げさなことではなく、目の前で死にそうな人がいるとすれば、その人に一片のパンを与えること」――正義とは、空腹の者にパンを与えること。
『アンパンマンの遺書』より
これが、やなせさんのたどり着いた“正義”の定義です。そして、アンパンマンの根っこにある考えなのです。
-------------------------------------
第二次世界大戦では、日本人の死者数はおよそ310万人。
そのうち、戦没した日本軍人・軍属は約230万人。
しかも、その多くは戦闘による戦死ではなく、食料の補給が絶たれたことによる“餓死”や関連する病死だったといわれています。
想像を絶する犠牲者数です。当時、日本の人口(1940年) 約7,300万人。
およそ4%もの人が、戦争によって命を落としました。
25人に1人という規模です。
お寺の過去帳を見ても、戦時中は戦死者の戒名がずらっと並んでいます。数が一気に増えている。
-------------------------
ご承知のとおり、今年は戦後80年という節目の年です。
曹洞宗の服部宗務総長が、去る5月15日で「アジア・太平洋戦争終戦80年を迎えて」という談話を発表しました。全文は配布している資料の通りです。
その中で、戦争の悲惨さ、そして当時、宗門が国家政策に迎合し戦争に加担した歴史を深く反省することが述べられ、「同じ過ちを二度と繰り返さぬよう」「努力していく」との誓いが示されています。
また先ほどお唱えした、お釈迦さまの「目に見えるものでも見えないものでも、すべてのいのちに幸いあれ」という慈悲の教え、道元禅師の「自未得度先度他」の心、そして瑩山禅師の「必ず和合・和睦の思いを生ずべし」という和の精神があらためて示されています。
-----------------------------
80年前の戦禍を経て、今ある、この豊かさと平和です。
戦時中と比べると、現代は「飽食」の時代といえるでしょう。
確かに、子どもの貧困や格差の広がりは社会問題となっていますが、それでも“食べ物がまったく手に入らない”という事態には、なかなか遭遇しません。
私も豊かな時代に生まれ育っています。
飢えを感じた体験はほとんどありませんが、ただ一つ、大本山永平寺での修行時代には、心底「空腹」を感じました。食べ物の有り難さが、身にしみてわかりました。
「空腹は人を変える」
NHK連続テレビ小説「あんぱん」の中でもそんなセリフが語られていますが、まさにその通りです。
戦争中は日本国中が、飢えと苦しみに耐えていた。国民すべてが、空腹に耐え、辛抱していたんだと思います。
---------------------------------
やなせさんは、ご自身の経験を通して「空腹で困っている人を助ける」 こと。その行いを「何にも代えがたい絶対の善」と信じ、アンパンマンにその想いを託しました。
-----------------------------------------------------------------
今回、このお話をするにあたって、私は一つ、大発見をしました。
やなせさんがアンパンマンを生み出すヒントにしたのではというもの。おそらく、ある存在をモデルにしてアンパンマンを生み出したのではないか……。
皆さん、何をモデルにしたと思いますか?
――そう、お地蔵さまです。
瓜二つじゃありませんか?
丸い顔、赤いマント、そして――子どもたちのヒーロー。
どこにでも現れて、困っている子どもを助ける存在。
「常に、弱き者の味方」。
お地蔵さまもまた、特に子ども、旅人、病人など、一切衆生生きとし生ける者、弱い立場にある人々を守ってくださる仏さまです。
正式には地蔵菩薩と言います。菩薩とは、衆生の世界において、衆生を救うことを誓った仏様です。
どうでしょう、間違いないですよね?アンパンマンは、お地蔵さまだったんです!
-----------------------------------------------------
アンパンマンの姿は決して“子ども向けのお話”にとどまらない。
仏教の説く「利他行」の精神そのものといってもいいでしょう。
子どもたちは、アンパンマンからその心を知らず知らずに吸収していると思います。
仏教の説く「利他」とは
◆ 仏の心「慈悲心」とは 慈悲×智慧
仏教では、「慈悲(じひ)の心」が、利他行の出発点とされています。慈悲心とはすべての生きとしいけるもの向けられます。
「慈」とは―相手の幸せを願う心。 『与楽』
「悲」とは――相手の苦しみを取り除こうとする心。『抜苦』
この慈悲の心が、「智慧」によって導かれ、行動となってあらわれたものが「利他行」です。困っている人を見て、ほうっておけない。
その自然に湧き上がる思いやりの気持ちこそが、仏教の理想とする「慈悲の心」なんですね。
修証義に見る仏教の利他の教
曹洞宗の宗典の一つである、修証義。皆様もご法事などで読経されることもあるかと思います。1章総序からはじまり、全部で5章あります。
修証義の第四章が「発願利生」という章で、「利生」は利他行と同じ意味です。
この第四章に道元禅師の利他行に関する教えが示されています。
第4章の冒頭は次のように書いてあります。
「菩提心を発すというは、己れ未だ度らざる前に一切衆生を度さんと発願し営むなり、設い在家にもあれ、設い出家にもあれ、或いは天上にもあれ、或いは人間にもあれ、苦にありというとも楽にありというとも、早く自未得度先度佗の心を発すべし」
度すとは、「渡す」とういう意味です。悟りの岸、彼岸に渡す。 時代劇で「度し難き奴よのう」とうセリフが出てきますね。「救い難き奴」という意味です。
「自未得度先度他」
これは、「自分自身がまだ悟りという岸に到達していなくても、まず他の人を彼岸に渡す」という意味です。
平たく言えば、「自分の救いよりも先に、他人の救済を願いなさい」ということ。
仏道を志す者は、自分のことばかり考えてはいけない。他者の救いを願い、行動する心が求められています。
アメリカのトランプ大統領が掲げた「アメリカ・ファースト」というスローガンは、「我が国の利益をまず第一に」という発想です。トランプさん交渉上手なので、言葉にインパクトがあります。
ただ、この「アメリカ・ファースト」という考え方は、「自未得度先度他」の精神とは逆方向のものと言えるでしょう
自未得度先度他の心は「After You」「お先にどうぞ」です。
ただ単に、「お先にどうぞ」では優しすぎる印象が強いのですが、こういう気持ちも秘められていると思うのです。
「大丈夫、先に行け!必ず後から行くから!」
自分はを信じて送り出す。そして自分もまた、そのあとを歩み続ける覚悟と決意。これこそが「自未得度先度他」の心なのではないかと、私は感じています。
具体的な実践徳目 「四摂法」
利他行どのように日々の行動として表せばよいのでしょうか?修証義の第四章において「四摂法(ししょうぼう)」が示されています。
これは、利他行の実践的な“行動の指針”実践徳目ともいえる内容です。四つあります。
四枚の般若あり
布施・愛語・利行・同事
布施――物や力を与えること。貪らざるなり
愛語――心から相手を想った、言葉をかけること。
時には厳しい言葉も必要かもしれない。回天の力あることを学すべきなり。
利行――人のために行動すること。
同事――同事というは不違なり。相手と共に在ること。共感。
4つ目の利行は、人のためにする行い、つまり利他行のことです。
そこでは利他行について本質的なことが説かれています。
このように書いてあります。
◆ 窮亀を見、病雀を見しとき誰か報謝を求めん
「窮亀を見、病雀を見しとき、誰か報謝を求めん」
意味は、
「困っている亀や、病気の雀を見たとき、誰が(助けた見返りに)お礼を求めるだろうか?――いや、求めはしないだろう」というものです。
つまり、苦しむ生きものを見たら、条件反射のように自然と手を差し伸べるのが本来の慈悲であり、
そのときに見返りを期待するのは、本来の利他とは言えない――という戒めです。
想像してみてください。
道ばたでひっくり返って足をバタバタしている亀を見かけたとき、多くの人は自然と、ひっくり返して助けてやるのではないでしょうか?
そのとき「助けてあげるから、お礼ちょうだい」「竜宮城に連れてって」と考える人はいないと思うのです。
歩いている人が何を落としたら、落ちましたよととっさに声をかける。仏教が説く利他行とは、まさにそうした純粋な慈悲の心から出発しなさいと説かれています。
利他行の落とし穴
皆さんはお寺でもお役をされている方ですから、地域でもいろいろなお役をされていることと思います。利他的な行動を日常的にされている。
ボランティア、奉仕、自発的であるか、頼まれて、断り切れずなどいろいろあると思いますが。
日本人は、思いやりを大切にして、人に親切にする文化を持っています。利他的な行いしている人がほとんどだと思います。しかし、よき行いである、利他にある落とし穴もあると感じています。
3つ紹介します。
落とし穴① 求める気持ちが苦しみになる
こういうことありませんか?
・手助けしたのに、お礼も言われなかった。
・心配して声をかけたのに、無視された。
・良かれと思ってやったのに、「余計なお世話」と言われた。
そんな経験は、誰しもがあると思います。
「せっかくしてあげたのに~」
「のにがつくと愚痴になり みつを」
誰かに親切にしても、「ありがとう」の一言が返ってこないと、がっかり・腹立たしい・怒り・虚しさ…… 身近なところでは、家族のために一生懸命尽くしても感謝されないと、「こんなにやってあげているのに」と不満が湧いてしまう。
お寺の奉仕や地域のボランティアでも、誰にも感謝されないとやる気がなくなる――
「感謝されたい」「認められたい」という思いが裏切られたとき、
人は落胆し、時に怒りさえ感じてしまいます。
しかしそれは、私たちの心の中に“求める気持ち”が混ざっていたからこそ起こる苦しみです。
仏教では執着が苦しみを生むと考えます。心に潜む求める気持ちにより、せっかくの善い行いが、苦しみや怒りの原因になるという落とし穴があります。
落とし穴② 利他行が自己犠牲になる
必ずしも、利他行は自己犠牲を強いるものではありません。 喜んでさせていただく。そこに犠牲的な感情はふさわしくありません。
アンパンマンの行動は自己犠牲でしょうか。「顔をちぎって差し出す」という行為だけを見ると、「自分を犠牲にして他者を助ける」と感じるかもしれません。
私は「自己犠牲」だとは思いません。
アンパンマンはためらうことなく顔を差し出します。
なぜなら、顔はまたすぐにジャムおじさんが焼いてくれるからです。
つまり“再生可能”なのです。ジャムおじさんや他の仲間の支えによって力を得る。
だからこそ、アンパンマンはいつもニコニコしています。
そして、再生する顔は、無限の慈悲心の象徴に感じます。
アンパンマンは、“自己犠牲”というよりも、心の底から「人を助けたい」と願い、行動する姿。
日本人は何に対しても真面目に取り組みすぎる場合がある。「利他疲れ」ということもあるんじゃないかと思います。他人から見て「大変そうだ」と思っても、自分がOKなら大丈夫だと思いますが、自分で負担感がひどい場合は、そこから離れることも大切です。 極度の自己犠牲に陥るという落とし穴です。
落とし穴③ 「あなたのために」に潜む 我欲
「あなたのためを思って」この言葉は言いがちですが、要注意です。 やっている本人は相手のことを思って行っている行為でも、その言葉や思いが相手のプレッシャーになる。この言葉の裏には、結局は自分の思い通りにしたい、という我欲があることが多いものです。
他人をコントロールするために、利他的な行いをする。
これも、仏教の目指す利他行ではなりません。
「あなたのため」は自分の勝手な思いかもしれない。
相手がどう感じ、どう反応するかは相手次第です。
「自分の我欲のために利他を行う」という落とし穴にも気を付けるべきです。
三輪清浄(空寂)という理想
仏教では、「三輪清浄(さんりんしょうじょう)」という理想を説いています。
「三輪空寂(さんりんくうじゃく)」ともいわれ、布施の究極のあり方をあらわす言葉です。
施す人(施者)、受け取る人(受者)、そして施す物(施物)。
この三つのどれにも執着を持たず、ただ自然に、当たり前のように行うこと――
それが、仏教の目指す「利他行」なのです。
「自分がしている」という意識さえ離れ、相手を下に見ず、行為を誇らず、執着やはからいを離れ、ただ自然に行ええたら、それが三輪清浄の姿でしょう。
「私は与えた」「やってあげた」「あなたは受け取った」「これは良い行いだった」その自分の意識からを離れて、ただ「自然に、息をするように行う」。
見返りを求める心: 自分の行いが評価されたい、感謝されたいという気持ち。
自己満足: 良いことをしたという優越感や自己肯定感を得たいという気持ち。
他者との比較: 他者よりも優れている、良い人間だと思われたいという気持ち。
執着: 良い結果や報いを期待する心。 これらのない利他行です。
人のために尽くす大切さは、仏教以外の教えや格言にもたくさん語られています。しかし、仏教は「したことさえも忘れる」程の境地。「三輪清浄」。
これが仏教の究極の利他行なのです。
(令和7年6月16日(月)~20日(金)「京都府宗務所 第7教区護持会 地区布教役員研修会」 法話より 前半部)